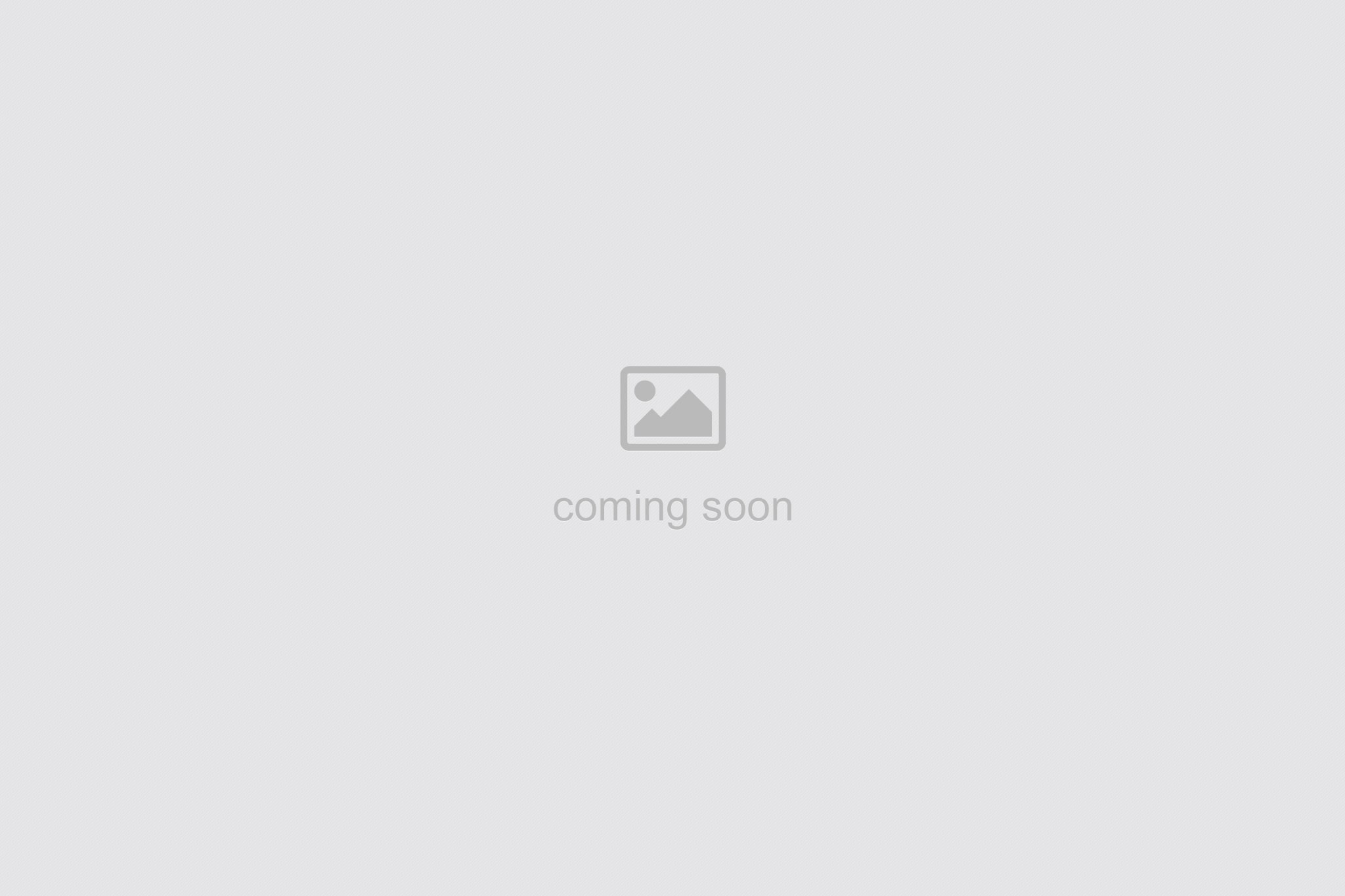山形大学菅野研究室の方々による金属材料基礎講座です。工業系学生の方々にもわかるようにまとめていただきました。
焼き戻し(工具:SKD:SKH)
焼き戻しは何故必要なのか
焼き戻しは、焼き入れ後に行う熱処理である。焼き入れした鋼には以下のような欠点がある。
- 焼き入れによって鋼はオーステナイトからマルテンサイトと呼ばれる素引きになる。このマルテンサイトは非常に硬い組織である。鋼は焼き入れたままでは非常に硬いが、その反面もろい状態、すなわち靱性が欠けた状態となっている。
- 焼き入れ後も材料内部にはマルテンサイト化していないオーステナイト(残留オーステナイト)が残っている場合がある。このマルテンサイトや残留オーステナイトは室温付近では不安定でこれが時間の経過とともに析出や相変態を起こし、その結果、材料の寸法や形状に変化を生じる。
- オーステナイトからマルテンサイトへの変態で、材料の外周部と内部では変態開始時期にズレがあり、また変態に付随して体積膨張を生じるため、材料外周部と内部との体積膨張差に基づく残留応力が生成し、そのために変形や割れを生じる恐れがある。 これらの欠点から、焼き入れ鋼がそのまま利用されることは少ない。そこで、不安定な組織を安定化し、靱性を改善し、また残留応力を取り除くための熱処理として焼き戻しを行う必要がある。
焼き戻し温度の基本的な設定
焼き戻し温度は、鋼が変態点(A1)以下の適当な温度に設定する。焼き戻し温度が高いほど硬さや強度は低下し、延性や靱性は増加する。焼き戻しは、その温度により、低温焼き戻しと高温焼き戻しの2種に大別され、延性や靱性を重視する鋼などでは高温焼き戻しを行い、硬さや強度を重視する鋼では低温焼き戻しを行う。
しかし焼き戻しの加熱温度は鋼の種類によって避けなければならない温度域がある。炭素鋼では250~350℃、Cr鋼やNi-Cr鋼などの合金鋼では450~550℃の温度域がそれにあたる。これらの温度域で焼き戻しを行うと靱性の著しい低下が起こる。これをそれぞれ低温焼き戻し脆性、高温焼き戻し脆性という。 よって、これらの特性を考慮に入れ、用途に応じて温度設定を行う。
低温焼き戻しと高温焼き戻し
・低温焼き戻し
低温焼き戻しは、焼き入れ後、150~200℃に一定時間加熱した後冷却する熱処理である。焼き戻し温度が低いので、硬さの低下を抑え、焼き入れによる残留応力を除去できる。低温焼き戻しは、硬さや耐摩耗性が要求される工具鋼や軸受け鋼などに用いられる。
・高温焼き戻し
高温焼き戻しは、焼き入れ後500~600℃に加熱した後冷却する熱処理である。焼き戻し温度が高いので、硬さや強度は低下するが、延性や靱性は向上する。高温焼き戻しは、強靱性が要求される機械構造用鋼、またSKDやSKHなどの工具鋼などに用いられる。
SKDやSKHなどの工具鋼は高温で使用されるため、高温で硬さを保持しなければならない。鋼の共晶温度直下約1000~1200℃で焼き入れを行い、500~600℃で焼き戻しを行うと、2次硬化したものは、この温度域まで再加熱しても硬さはほとんど低下しないので、高温で硬さを保持することができ、高温での使用を可能にする。
以上:山形大学 工学部 機械システム工学科 -卒業- 和田 洋介
二次硬化
二次硬化は何故起きる
焼き戻しが進行するとセメンタイトが凝集して大きくなるために著しく軟化していく。しかし、鋼に炭化物を形成しやすい特殊元素が含有されている場合には、軟化の度合いが鈍くなる。つまり、焼き戻し軟化抵抗を示すようになる。焼き戻しには、低温焼き戻しと高温焼き戻しがある。
鋼の場合、400℃以上のいわゆる高温焼き戻しを行うと、特殊元素との炭化物が析出するようになる。それらの現れる温度及び析出の様相は含有元素の種類によって多少異なるが、多くは焼き戻し温度400~650℃の範囲に現れ、炭化物析出により硬化現象が起こる。
この現象は、この温度域になると合金元素の拡散が充分起こりえるようになり、しかも合金元素が鉄よりも炭化物生成傾向が強いため、既に存在しているセメンタイトに代わって独自の炭化物を形成することにより起こるものである。
また、焼き入れの段階でマルテンサイト化しなかったオーステナイトを残留オーステナイトと呼ぶ。高温焼き戻しでオーステナイトの状態で特殊炭化物を析出した残りの地は、Ms点(マルテンサイト変態開始点)が上昇するために冷却(急冷)の途中にマルテンサイト化が起こる。ここでも硬化が起こり、これらの現象を2次硬化という。
二次硬化しない材料とする材料
炭化物生成元素のMo(モリブデン)、V(バナジウム)、W(タングステン)、Nb(ニオブ)、Ta(タンタル)、Ti(チタン)等はセメンタイトに固溶しにくく、2次硬化を起こす。またCr(クロム)はセメンタイトにはかなり固溶し、焼き戻し軟化抵抗を示すが、2次硬化は起こしにくい。 非炭化物生成元素のNi(ニッケル)、Al(アルミニウム)は焼き戻し課程にほとんど影響を及ぼすことがない。Si(ケイ素)、は軟化を遅らせる働きがあり、Mn(マンガン)はセメンタイトに固溶して耐焼き戻し性を増す効果がある。Cu(銅)、Au(金)は単独で析出し、合金炭化物の分布や大きさに間接的に影響する。
二次硬化の利用
強度が上がるため、構造物や橋などに利用される材料に応用される。また600℃くらいまでの高温で使われる工具類にも利用される。これは残留オーステナイトが高温で不安定になることを防ぐためである。
以上:山形大学 大学院 理工学研究科 機械システム専攻 -卒業- 菱田 憲司
マルテンサイトとオーステナイトについて
オーステナイト
γ鉄(911~1392℃)に炭素を最大2.1%まで固溶した固溶体組織。結晶構造は面心立方晶系で、炭素は面心立方格子の中に侵入型で固溶している。常温に置いては不安定組織であるが、A3変態点以上の温度でのみ安定な組織である。炭素含有量に応じて、オーステナイトは物理的及び機械的性質が異なる。
たとえば、炭素量の多いオーステナイトほど硬さは大きくなる。オーステナイトは非磁性体で電気抵抗は大きい。常温加工を施せば、マルテンサイトに変化する。顕微鏡的には多角形の組織を示す。炭素鋼においていかに急冷してもオーステナイトのみの組織は得られない。焼き入れ鋼におけるオーステナイトの量は高炭素鋼ほど、また焼き入れ温度の高いものほど多く、最大量は50~60%に及ぶ。
マルテンサイト
高温のオーステナイト状態から焼入れたときに得られる微細緻密な針状組織。結晶構造は炭素を過飽和に固溶する体心正方晶系(α-マルテンサイト)と面心立方晶系(β-マルテンサイト)がある。鋼を水焼入れ した時にできるのがα-マルテンサイト、これを100~150℃に再加熱すれば炭化物の析出により結晶軸(c軸)が収縮してβ-マルテンサイトに変化する。
いずれも常温では不安定組織である。鋼の焼き入れ組織の中で最も硬く、脆く、強磁性を示す。オーステナイトよりも密度が低いため、オーステナイトからマルテンサイトへの変化の際に体積膨張を起こし、著しく容積を増す。顕微鏡的には木の葉状または針状の組織を示す。炭素鋼では、急冷の課程ではある程度に達すると自然発生的に生じ、水冷却した時に最も多く現れる。
以上:山形大学 大学院 理工学研究科 機械システム専攻 -卒業- 鎌田 拓
疲労強度と靭性値
疲労強度
たとえば、材料の引張り強度が100MPaとした場合、材料に100MPaより大きな力がかかったと壊れます。逆に100MPa 以下の力が作用すれば壊れません。しかし50MPaや60MPaの力が作用する場合に、強度的には壊れるはずがない材料でも、小さな力が何万回、何億回と繰り返し作用することにより壊れてしまうことがあります。
このように、普通なら壊れないはずの力でも、繰り返しの効果によって壊れる現象を材料の疲労と言います。疲労強度とは繰り返しの作用を受けても実用上材料が永久に壊れないと判断される力の最大振幅の大きさです。
靱性
材料の特性評価の仕方にはいろいろあります。たとえば静かに材料を引張るとき、どれくらいの力でどれくらい伸びるかどうか。一方、靱性もその一つで衝撃力を加えたときに材料が破壊するまでにどれだけのエネルギーを必要とするかについて示す尺度です。衝撃的に大きな力を加えたときに破壊しにくい材料を粘りがある、「靱性」が高いといいます。靱性の目安は静かに材料を引っ張って破壊させたときの力と伸びの積として仕事量で表すことができます。つまり、材料が大きな力に抵抗しながら、長さは伸びるけれども破壊しない材料を“靱性が高い”と言います。
両振り疲労試験
実際の材料にかかる力(応力)は刻々と変化します。材料にかかる応力の形態には引っ張り、圧縮、曲げ、ねじりがあります。実際は材料の疲労現象を解明するために簡単にした荷重パターンを用いて疲労試験をするのが普通です。そこで用いるのがそれぞれの形態に対して正および負側に等しい大きさの応力が繰り返される場合の両振り疲労試験です。反対に最小応力が0になる場合、すなわち平均応力と応力振幅が等しくなるように応力が繰り返せられる場合を片振り疲労試験といいます。このような疲労試験の応力を簡単に表す方法として応力比Rがあります。
式は
で表せます。 またR=-1に相当するときの疲労試験を完全両振り疲労試験といいます。
以上:山形大学 大学院 理工学研究科 機械システム専攻 菅野研究室 -卒業- 安部 典昭